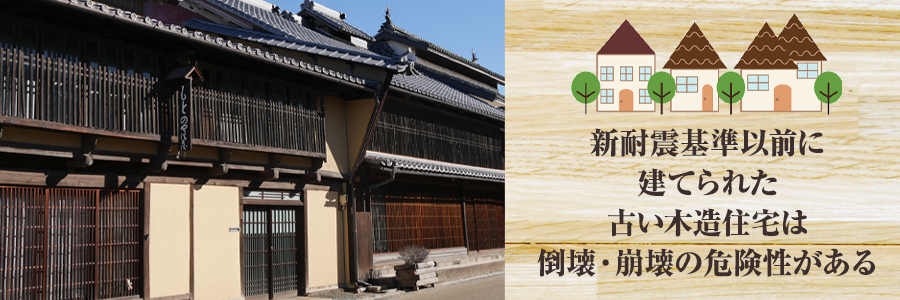木造住宅は人気がありますが、「耐震性が低いのではないか」と不安を抱く方も少なくありません。特に日本は地震大国であり、安全な住まいへの関心は高まっています。実際に、2000年基準を満たしていない木造住宅は、大規模地震で破損・倒壊するリスクが高いため、注意が必要です。
この記事では、木造住宅の耐震性や、住宅の耐震性能を決めるポイント、地震に強い木造住宅を実現するための耐震・制震・免震工事の違いについて解説します。安全で安心な住まいを実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
1. 木造住宅の耐震性は低い?
木造住宅の耐震性はRC造住宅と比べると低めですが、木材が金属よりも地震に必ずしも弱いわけではありません。ただし、木造住宅はRC造の住宅より劣化しやすいため定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスが足りていない場合、着工時点では耐震性能に問題がなくても、劣化により耐震性能が低下する恐れがあるため注意しましょう。
特に、新耐震基準に沿って建てられていない古い住宅の場合、適切な耐震リノベーションが施されていなければ倒壊・崩壊の危険性があります。
旧耐震基準とは、1981年5月以前の耐震基準を指します。対して、同年6月に施行された建築基準法によって制定されたのが新耐震基準です。新耐震基準では、震度5強程度では軽微な損傷にとどまり、震度6強~7程度でも建物が倒壊しないことを義務づけています。
さらに、阪神淡路大震災による被害状況の検証を受けて2000年6月には耐震基準が改正され、地盤調査や基礎構造、壁などに関する規定が厳格化されました。耐震基準は大規模地震などを機に強化された経緯があるため、旧耐震基準で建てられた住宅の耐震性は低い傾向があります。
1-1. 2000年5月以前に建てられた住宅の場合倒壊の危険あり
木造住宅の場合、新耐震基準に沿っていても2000年5月以前に着工している住宅は、大地震の際に倒壊する危険があります。2000年基準を満たしていない場合は、耐震リノベーションも検討しましょう。
熊本地震における、2000年6月以降に建てられた木造住宅の倒壊・崩壊率は全体の2.2%です。一方、1981年5月以前に建てられた木造住宅は28.2%、2000年5月以前に建てられた木造住宅は8.7%が倒壊・崩壊したという調査結果が出ています。さらに、2000年5月以前に建てられた住宅が被害を受けなかった割合が20.4%なのに対して、6月以降に建てられた住宅の無被害率は61.4%でした。
日本耐震診断協会のデータによれば、1981年6月から2000年5月までの期間に建てられた木造住宅の約8割は震度6強の地震で倒壊する可能性があります。このうち、「倒壊する可能性が高い」とされる木造住宅は61%です。
出典:日本耐震診断協会「「新耐震」でも倒壊の恐れ 2000年5月以前の木造住宅」
2000年基準を満たしているかどうかで、住宅の破損リスクは大幅に変わると言えるでしょう。
2. 木造住宅の耐震性能を決めるポイント
建物の耐震性を示す基準の1つが耐震等級です。耐震等級は等級1~等級3まで3段階に分かれています。等級1は、建築基準法が定める最低限の耐震性能を満たす水準です。
| 耐震基準 | 耐震性能の目安 |
|---|---|
| 耐震等級1 |
震度5程度の地震ではほとんど損傷しない 震度6強~7の大地震でも倒壊・崩壊しない |
| 耐震等級2 |
耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つ 長期優良住宅の最低基準 |
| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持つ |
災害に備え、家の資産価値を落とさないためにも、定期的に耐震診断を受け、必要に応じて耐震リノベーションを行いましょう。リノベーションによって確実に耐震性能を高めるために押さえたほうがよいポイント4つを以下で説明します。
2-1. 建物の重さ
建物は重量が重いほど、地震の揺れや衝撃をより大きく受け、負荷がかかります。軽い建物の耐震性は一般的に、重い建物よりも高めです。重量の観点からは、鉄筋コンクリート造や鉄骨造よりも軽い木造住宅は耐震性が高くなります。
木造住宅の屋根や外壁に軽量な建材を用い、さらに建物を軽くすれば、耐震性能をさらに高めることが可能です。例えば、従来の屋根瓦ではなく鋼板などの軽量屋根材を用いると、屋根の重さは軽くなります。外壁にも金属系や樹脂系などの軽量な板材を用いれば、耐震性の向上につながります。
2-2. 耐力壁と柱の数
耐力壁と柱の数は多いほど、建物の耐震性が高まります。耐力壁とは、地震による揺れや台風の暴風など水平方向からの力や、建物の重さによる垂直方向からの力に対して建物を支える壁です。耐力壁には筋交いや構造用合板などを用い、強度を上げています。
柱は、建物の重さなど垂直方向にかかる力に対して建物を支える役割を果たしています。耐力壁と柱を組み合わせて適正な数をそろえると建物にかかる横や縦からの力に対抗でき、耐震性が向上するでしょう。
2-3. 耐力壁の配置
リノベーションする際は、耐力壁の数とともに配置を考慮する必要もあります。耐力壁を偏りなく、バランスよく建物に配置することで、耐震性は高まります。建物の一部に集中させると、耐力壁がない場所から建物の変形や倒壊につながる可能性があるため要注意です。
2階建ての木造住宅では、耐力壁を設ける位置を1・2階で合わせると、地震による負荷を2つの階で分散できるというメリットがあります。上下、前後左右からの力に耐えられるように耐力壁を配置することを心がけてください。
2-4. 床や基礎部分の強さ
床は建物の重さによる垂直方向からの力を支えているのみならず、揺れや風など水平方向からの力を受ける壁とも床はつながっています。建築段階で床の補強を行い、耐震性を強めておくと、耐力壁にかかる負荷を分散できるというメリットもあります。
建物の基礎部分は、建物を支える重要な部分です。このため、硬質な地盤に基礎部分を構えることが重要です。基礎部分を構える工法には複数の種類があります。中でも耐震性に優れている工法は、格子状に鉄筋を入れてコンクリートを打つベタ基礎と言われています。
3. 地震に強い木造住宅を作る耐震・制震・免震工事の違い
木造住宅の地震対策工事には耐震・制震・免震という3種類の方法があります。費用は高くなりますが、より地震に強い建物にするために、2つ以上の地震対策を併用することも効果的です。以下では、各工事の概要や特徴について詳しく解説します。
3-1. 耐震
耐震とは、地震の揺れに持ちこたえられるように建物自体の強度を高める方法です。強度の高い建材を用いるとともに、建物自体の強度を高めるさまざまな補強方法を組み合わせて耐震性を高めます。
例えば、柱の間に斜めに建材を取り付ける筋交いは、水平方向の力に対して建物を支える方法です。比較的安いコストで施工できる点はメリットです。また、柱や梁など構造体の間に強度の高いパネルを取り付けると、揺れの負荷をパネルに分散する効果を期待できます。
柱と梁、柱と土台などの接合部を金物で固定して補強すると、地震の揺れを受けても接合部が外れにくくなり、倒壊の防止につながります。
耐震工事は地震に耐える強度を住宅に持たせる目的で行われるため、住宅そのものは一定のダメージを受ける点に注意が必要です。制震・免震など、地震の揺れを吸収できる工事と併用すれば、耐震性能をより高められます。
3-2. 制震
制震とは、建物の内部に設置した装置に地震の揺れを吸収させて建物の損傷を防ぐ方法です。免震と比べて、既存住宅にも設置しやすい点がメリットです。一般の戸建て住宅以外にも高層ビルなどの建物にも採用されています。
制震に用いる主な装置は、ゴムダンパー・オイルダンパー・鋼材ダンパーの3種類です。
ゴムダンパーは、ゴムが伸縮して地震エネルギーを吸収します。繰り返し発生する地震にも対応する反面、気温の変化が激しいと性能を十分に発揮できない点はデメリットです。
オイルダンパーは、オイルの粘性抵抗を生かして地震エネルギーを吸収する装置です。地震だけでなく強風による揺れにも対応でき、リノベーションの際に間取りに制限がかからない点がメリットです。ただし、数多く設置する必要があり、総費用が高くなりやすい点はデメリットと言えます。
鋼材ダンパーは、地震の揺れで金属が曲がり、地震エネルギーを吸収します。比較的安く設置でき、メンテナンスの手間がかからないメリットがありますが、揺れを繰り返し吸収すると金属疲労による破損リスクがある点がデメリットです。
3-3. 免震
免震とは、地震の揺れが建物に伝わらないように、地盤と建物の基礎を切り離し、地震エネルギーを吸収する装置を建物の下に設置する方法です。地震によって地面が動いても、建物に伝わる揺れを装置が極力抑えるため、家具の転倒や損傷も減少できます。
免震で用いる主な装置には、積層ゴム支承・転がり支承・すべり支承があります。積層ゴム支承は、ゴムと鋼板を交互に重ねた装置です。ゴムが揺れを緩和し、鋼材で建物を支える仕組みです。
すべり支承は、柱の下に施したすべり材がすべり板の上を滑り、地震の揺れを緩和します。転がり支承は、地震時に建物の重さを支えるボールベアリングがレールを転がって移動し、揺れを緩和します。
免震は地震のエネルギーによる被害を最も小さくできるとされる工法ですが、リノベーションの際に導入する場合、基礎部分の大規模な工事が必要です。したがって、免震リノベーションは耐震・制震リノベーションより高コストになりやすい点がデメリットです。
まとめ
木造住宅の耐震性は、建築年代や設計、メンテナンス状況によって大きく左右されます。特に2000年以前に建てられた住宅は、耐震基準の違いから地震に対する脆弱性が高い可能性があります。
耐震性能を高めるためには、建物の軽量化や耐力壁の適切な配置、床や基礎部分の強化など、設計段階での工夫が重要です。また、耐震、制震、免震といった地震対策工事を適切に組み合わせれば、建物の揺れを軽減し、損傷を防ぐことが可能です。特に、耐震工事と制震工事は、免震と比べてリノベーションのコストが小さいため、組み合わせて導入すれば地震に強い家作りができるでしょう。